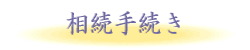|
|
|||||||||||||||||||||||
相続とは「相続」とは個人の財産に係わる様々な義務と権利が、個人の死後、法律上定められた一定の者たちへ継承されることを言います。この際、亡くなった個人のことを「被相続人」といい、財産を承継する人のことを「相続人」と呼びます。 財産とは、お金や不動産だけでなく、貸借の権利と義務も含まれます。 被相続人が他人にお金を貸していた場合には、そのお金を返してもらう権利が発生しますし、他人からお金を借りていた場合には、 そのお金を返す義務も発生することになります。 |
| 相続の開始 |
|
人が亡くなると相続が開始されます。まずは相続人を確定するために、相続人の調査をしなければなりません。
家族構成が複雑でなければ相続人も簡単に決まるのですが、離婚(養子縁組)等によって家族構成が複雑になっている場合は相続関係も複雑になります。 相続が発生した時に相続手続きをしないでいると、相続人である子供も亡くなり、孫が相続人となっている状態になってしまいます。 この状態を数次相続と言い、子や孫だけでなくその兄弟等が絡むと相続人が大多数になったりしますので、相続の手続きは早めに済ませておくに越したことはありません。 |
| 相続人 | ||||||||||||
|
相続人には相続順位があり、民法により規定されています。 最優先順位は配偶者です。続いて子→親→兄弟という順番になります。
以上が法で定められた原則ですが、相続の放棄・相続欠落などの理由により、相続分が複雑に変化する場合があります。 |
||||||||||||
| 相続の放棄 |
|
相続人は相続開始時から3ヶ月以内であれば相続を放棄することが出来ます。 手続きは家庭裁判所へ[相続放棄の申述]の書類を提出するだけなので簡単です。 相続を放棄することによって被相続人の財産が一切相続出来ません。 例えば被相続人の借金が多く、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が明らかに多い場合などに相続放棄されることが多いです。 |
| 相続人の調査 |
|
相続人の調査をするには、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を全て調べなければいけません。
戸籍謄本は転籍や婚姻などで複数ある場合がほとんどなので、通常1通ではおさまりません。 この戸籍謄本の記載から配偶者の有無・子供の人数など、各法定相続人の法定相続分などが分かります。 |
| 遺産分割協議書 |
|
遺産分割協議書とは被相続人の財産を相続の人間でどのように分割するかが記載された書面です。
法定相続分通りに遺産相続するなら必要ありませんが、偏った分割をする場合には必要になります。 例1)長女は親の面倒をよく見たので相続分を多めにするといった場合。 例2)土地は長男に全て相続し、現金は次男に全て相続するといった場合。 遺産分割協議は相続人全員によって行わなければなりません。 代理人での協議も可能ですが、必ず全員の参加が必要です。 全員の合意の下、遺産分割協議書を作成します。 書類について特に決まった書式はありませんが、 大事な項目を抜かすと後々問題が発生することがありますので作成の際には注意が必要です。 |